日本蛾類学会2024年秋の例会報告
2024年度の日本蛾類学会秋の例会は、昨年に引き続き、日本鱗翅学会関東支部との合同開催として2024年10月5日(土)に東京大学で催行されました。
参加者は蛾類学会および鱗翅学会の会員はもとより、鱗翅目に関心のある熱心な小学生も含めた会員以外の方を含め合計102名の参加をいただきました。
開催に先立ち、本会の枝会長より挨拶が行われました。その後は鱗翅学会関東支部、蛾類学会のそれぞれで以下のプログラムの示す通り、一般公演3題、招待講演2題の発表、意見交換が行われました。
- 一般講演1 (鱗翅学会)※〇は発表者
・〇牧田 習・矢後勝也・遠藤秀紀:南日本における気候変動がチョウ類の分布に与える影響
・森 晋一郎:世界の昆虫切手
・石塚正彦:夏に消えるキタテハ
- 一般講演2 (蛾類学会)
・中尾健一郎:LepiLED Maxi Switch 1.5を使った台湾での夜間採集経験
・〇荒島 彈・屋宜禎央・広渡俊哉:チャグロマダラヒラタマルハキバガ Drepressaria spectrocentra Meyrick, 1935(チョウ目:ヒラタマルハキバガ科)の正確なタイプ産地の情報および新寄主記録について
・荒井 周:ヒラツボカレハ(カレハガ科)の加計呂麻島からの発見とKunugia属の潜在的針葉樹食性について
- 招待講演1 (鱗翅学会)
森中定治(日本鱗翅学会関東支部) :私の歩いてきた道 カザリシロチョウ研究とともに
- 招待講演2 (蛾類学会)
Alessandro Bisi(イタリア) :The current status of Butterflies and Moths in Italy
蛾類学会の発表の概要は以下の通りです。
中尾氏の発表では、近年売り出されたLepiLED Maxi Switch 1.5(新しいライトトラップの光源)を使って行った台湾における採集状況の報告と、本光源が今後の採集でも有用である旨の報告が行われました。
荒島氏他による発表では、近年盛んなミクロを扱った研究で、これまで不明確であったチャグロマダラヒラタマルハキバガのタイプ産地について詳細な調査をもとに判明させるとともに、その生態や新たに判明した寄主植物の報告が行われました。
荒井氏の発表では、最も新しいカレハガの新種ヒラツボカレハを新たに加計呂麻島から発見するとともに、その針葉樹を食樹とする生態について考察が発表されました。
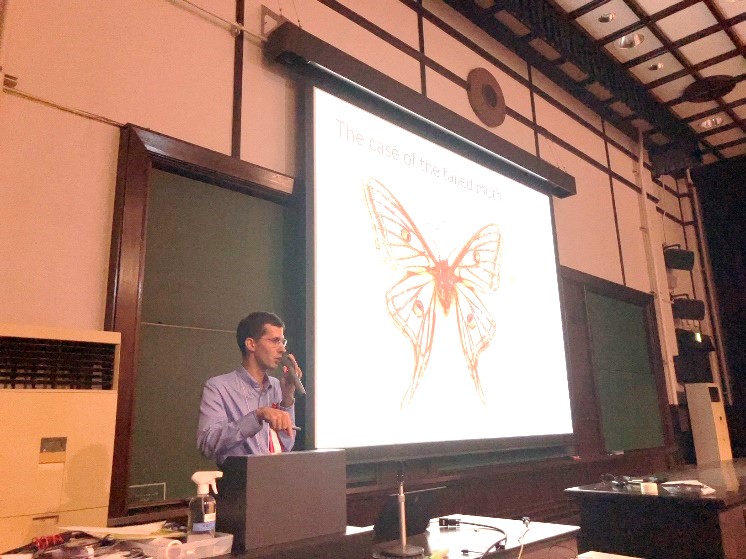
招待講演のBisi氏
招待講演は、9月に京都で行われた国際昆虫学会に参加し、その後日本の各地を周られていたイタリアのAlessandro Bisi氏(イタリアの鱗翅目の若手研究者でイタリアの鱗翅類について、多くの情報を発信しています)によるイタリアにみられる鱗翅類について講演いただき、イタリアの地形や気候の紹介とともに、注目すべきチョウやガについて熱く語っていただきました。講演後の懇親会では、Bisi氏をはじめ発表者の方と多くの参加者が意見交換を行い、充実した秋の一日を過ごしました。

Last update: 20 Jan, 2025
